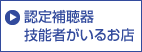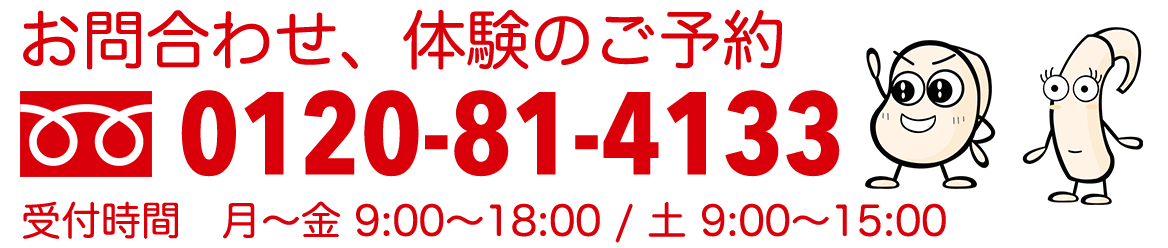2025年11月15日~26日の期間で開催されております東京2025デフリンピック。
耳が聞こえないアスリートのための国際的なスポーツ競技大会です。
100周年となる同大会は今回が日本での初開催となります。
今回またとない機会と思い、休暇を利用して同大会のボランティアとして参加しました!本記事ではその際の雰囲気をちょっとでもお伝えできればと思います。



東京2025デフリンピックは一部種目を除きほとんどの競技は東京都で開催されております。私が参加したのは福島県楢葉町のJヴィレッジで開催されました「デフサッカー」の大会運営のボランティアスタッフとして活動してきました。
◆デフサッカーについて
「デフ」とは英語で「deaf(聞こえない人、聞こえにくい人)」という意味で、ろう者(デフ)サッカーとは、聴覚障がい者のサッカーであり、競技中は補聴器を外すことが義務付けられていることから「音のないサッカー」の愛称で呼ばれています。ピッチ上ではアイコンタクトや手話でコミュニケーションを取っています
難聴の程度に個人差はあれど、競技中は補聴器などを外してプレーを行うため、通常のサッカーと同じ笛の合図だけでは不十分です。そのため通常のサッカーとは異なり主審もフラッグを持って笛とフラッグの2つの合図で試合をコントロールします。

(↑フラッグで合図を送る主審)
また上記写真には写っていませんが、今回のような国際大会ではゴール裏にもフラッグを持ったレフェリーが立ちます。主審、副審と合わせて計5名のレフェリーによって、選手たちが試合の状況を多方向から確認できる体制となっていました。
ただそれ以外の部分は通常のサッカーと全く同じルールです。選手の方々の動きも激しく、迫力のある試合ばかりでした。会場内ですれ違った海外選手の体格にも圧倒されました(笑)
試合中にコーナーキックなどのセットプレーでは選手同士が手話やハンドサインで攻撃を組み立てる姿も印象的でした。
またスタジアム内には電光掲示板が多方向に設置されていました。
写真の画質が悪く文字が潰れてしまっていますが、会場アナウンスの内容が字幕で視覚情報としても分かるように配慮がされていました。

(↑仮設の電光掲示板)
実際に活動を通してみて、アスリートの方々はもとより、一緒にボランティアを行うスタッフの中にも、ろう話者の方や、手話をメインにしながら口話でもやり取り可能な方など、さまざまな方と接する機会があり貴重な経験となりました。
正直なところ普段私たちが店頭での主な業務として応対する時とは違い、手話でのやり取りを求められる状況も多く、もどかしいと感じるような場面がたくさんありました。
しかし、覚えたばかりの拙い手話や様々なコミュニケーションツールを駆使して、曲がりなりにも意思疎通ができた時には、月並みな言い方ですが最終的には伝えようとする気持ちが大切だとも感じました。

東京の会場では入場規制がされるなど、これまでなかなか認知される機会が少なかったデフリンピックが注目を集めた大会でもあったようです。
聴覚に関することを扱う業界にいるので、こういった競技があることを少しでも多くの方に知ってもらい、世間での認知度が高まっていってほしいなとも感じました。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
長文、失礼しました。